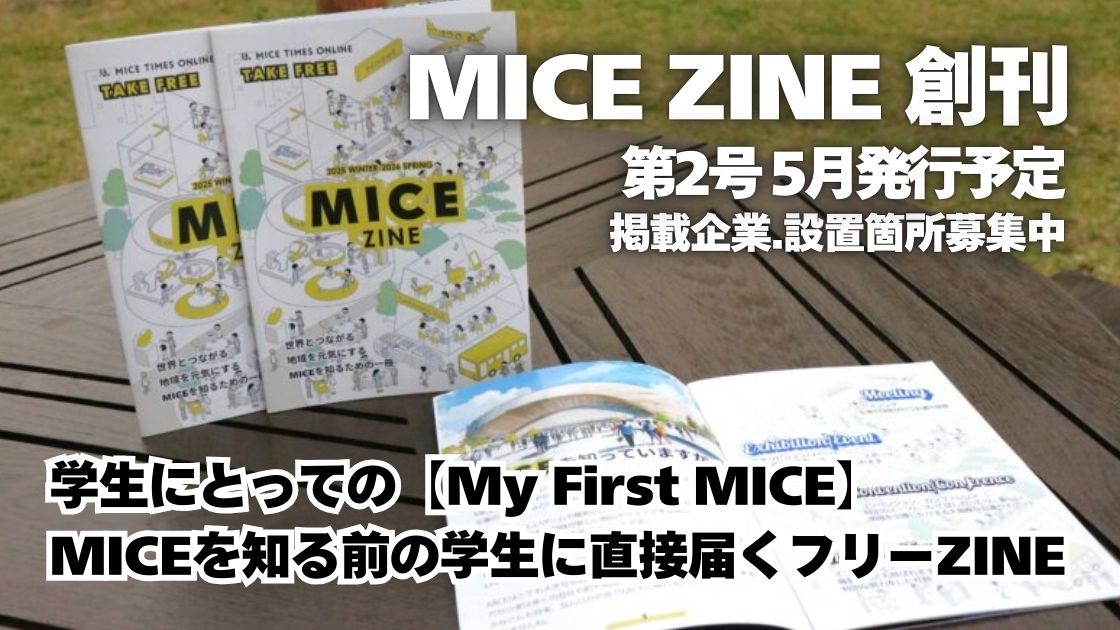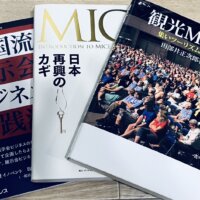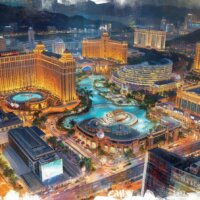【MICEの基礎知識17】企業によるプライベート展示会。その意義や特長、業界、実例を解説。MICEにおける位置づけは?
企業が取引先やグループ企業を中心に招待して実施するプライベート展示会をご存知でしょうか。企業によってはコーポレートイベントの一環として自社単独の展示会を開催するケースも少なくありません。本記事では「企業のプライベート展示会」に焦点を当て、どのような業界でどのような目的で開催されているのか、さらに実例を見ていきます。また、MICEの概念においてはどのような位置づけとなるのかにも触れていきます。

1. はじめに:MICEにおける企業プライベート展示会の意義
MICEとは、Meeting(会議)、Incentive(インセンティブ旅行)、Convention/Conference(国際会議や学術会議など)、Exhibition/Event(展示会・イベント)の頭文字を取ったビジネスイベント、ビジネストラベルを表す総称です。企業活動のなかで馴染み深いのはMeeting(社内外の会合)とExhibition/Event(展示会やイベント)ですが、このうち企業が自らのビジネスパートナーを招いて開催する展示会やイベントは、BtoB取引が中心となる日本企業のビジネスにおいて非常に重要な意味を持ちます。
一般公開型の展示会や、大規模な合同展示会とは異なり、プライベート展示会は対象者を企業が限定的に選定し、より深い内容の商談やビジネスパートナーとの情報共有がしやすいのが特徴です。こうしたイベントはコーポレートイベントの形態を取りながらも、取引先・顧客との結束を強め、新製品の発表や市場開拓の一手段としても活用されています。
2. プライベート展示会の定義と特徴
「プライベート展示会」とは、特定の取引先やビジネスパートナー、グループ企業など、主催企業があらかじめ選んだ限定的な来場者を対象に行われる展示会を指します。一般的な展示会の場合、不特定多数の来場者が見込まれ、入場料の有無や開催場所をオープンな場にすることで広く参加者を募る形が多いですが、プライベート展示会では事前に招待状を発送し、企業が来場者をコントロールすることで「より質の高いコミュニケーション」が可能となります。
まとめると、次のような特徴が挙げられます。
- クローズドな環境
企業内部の情報や最新技術などを安心して披露できる。競合他社の視線を避けながら、参加者との濃密な対話ができる。 - 対象者の選定
既存顧客や重要取引先、グループ会社など、ビジネス上重要な関係者を優先的に招待できる。担当者だけでなく、上層部や役員クラスも招くことで意思決定のスピードアップを狙うことが多い。 - 参加者へのホスピタリティ
企業は会場選定や催事内容で工夫し、特別感を提供する。宿泊・移動手配を含む手厚いサポートや、懇親会などの交流機会を設けることで関係強化を図る。 - きめ細かな情報交換・商談
大規模な一般展示会とは異なり、行列や雑踏が発生しにくく、担当者が来場者一人ひとりに時間をとって説明・交渉できる環境を作りやすい。
3. 招待される取引先・グループ企業の属性
プライベート展示会や取引先向けコーポレートイベントに呼ばれるのは、どういった方でしょうか。
- 取引先企業の担当者やバイヤー
小売店や代理店、卸業者などが該当。具体的な新製品の仕入れや発注を決める役割を担う場合が多い。 - 取引先企業の上司・経営層
重要商談や長期的な提携を視野に、役員クラスや社長層を招いて直接コミュニケーションを取る。これにより現場レベルでは得られない決裁を即時に得ることも可能。 - グループ会社の幹部・関係者
同一グループ内でのシナジー創出や事業連携を目的として、自社グループ企業を集めるケースも多い。 - 業界団体・メディア関係者・自治体関係者
新技術や新サービスを広報する意図がある場合、報道関係者や行政担当者を呼び、認知度を高める場とする場合がある。 - 株主や投資家(場合によっては)
非公開の情報を含むデモンストレーションを行うことで、企業価値や成長戦略をアピールする機会になることもある。
このように、招待客が企業のビジネスにとって極めて重要なステークホルダーである点がプライベート展示会の顕著な特色といえます。

4. 開催される主な業界と開催目的
企業のプライベート展示会や取引先招待イベントは、幅広い業界で活発に行われています。開催されることの多い主要な業界とその開催目的・特徴を整理してみます。私が昔、務めていたコンビニ業界ではFC本部が加盟店オーナーを招いたイベントが年に2回程度開催されていました。出展するのは本部だけではなく、弁当やパンのメーカー、清掃用具のメーカーなども招かれ、最新の照明や什器も展示され、加盟店のオーナーを本部のスーパーバイザーがもてなすような形が取られていました。
業界によって様々なスタイルのプライベート展示会が開催されているといえます。
製造業(工作機械・電子機器・自動車など)
- 新製品・新技術のデモンストレーション
工作機械メーカーや電子部品メーカーでは、実際に機械を稼働させたり、試作段階の新技術を対面で説明したりすることが多い。特に工作機械分野では大掛かりな機械を設置し、実機運転デモを行うケースが典型的。 - 商談・受注獲得
大規模な展示会に出展する場合と異なり、競合のいない環境で来場者とじっくり商談できる。製品のスペックやコストメリットを直接アピールできるため、受注確度を高めやすい。 - 先端情報の共有
産学連携やグローバル展開など先進的なテーマを扱う企業もあり、取引先に「今回だけ」「この場だけ」の情報を提供することで差別化や優位性を強調する狙いがある。
食品・消費財業界
- 小売・流通業者への新商品紹介
食品メーカーや日用品メーカーは、新シーズンに向けた新商品の発表やプロモーション施策をまとめて提示し、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのバイヤーにPRする。 - 販促施策の説明と取引条件の打ち合わせ
展示エリアで試食・試用体験を提供しながら、来年度の販売計画や販促キャンペーンを細かく相談する。これにより流通との協力関係をより強固にする。 - グループ企業の統合的アピール
大手食品企業の場合、グループ各社が同じ会場にブースを設け、総合力を示すことで取引先の信頼度を高める。
情報通信・IT業界
- 最新ソリューション・サービスの体感型展示
生成AI、クラウド、IoT、セキュリティなどの先端領域を中心に、来場者が実際に触れられるデモ環境を用意し、導入メリットを体感させる。 - 顧客課題のヒアリングと共創提案
企業の課題をその場で聞き出し、ソリューションチームがリアルタイムで提案する仕組みを設けることが多い。顧客との協力・共同プロジェクトに発展するケースもある。 - ブランドイメージ向上とネットワーキング
大規模フォーラム形式やカンファレンス形式を取り、パネルディスカッションやセミナーで知見を共有しながら、エグゼクティブとのコミュニケーション機会を創出する。
近年ではAppleが関係者を招き新製品を発表する「Apple Special Event」のように、その内容が一般のユーザーから大きな注目を集めるイベントもあります。
ファッション・アパレル業界
- シーズンごとの新作コレクション発表
アパレルメーカーやブランドは春夏・秋冬など、シーズンごとに展示会を開催して小売店バイヤーに向けて新商品を披露し、発注を受ける。世界観を演出したブースデザインが特徴。繊維素材メーカーがその素材を活かした提案を行うようなプライベート展示会も行われる。 - 受注会を兼ねた商談
展示会期間中にそのままオーダーを受け付け、商品生産数や出荷計画に直結させる。ファッション雑誌やインフルエンサーなども招かれ、話題づくりにも活用される。
その他の業界(サービス業・金融・医療など)
- サービスプレゼンテーションと顧客対応
金融機関やコンサルティング企業が、特定顧客向けにセミナー形式のイベントを開き、新商品・新プランの案内を行うケースも増加傾向。 - 医療・ヘルスケア業界
製薬会社や医療機器メーカーが院内向け、もしくは医師・医療従事者を限定して最新の治療技術や医療機器を紹介する展示会を開催することもある。

5.コーポレートイベントとしての位置づけ
プライベート展示会はしばしばコーポレートイベントの一部として位置づけられ、企業が主催する様々な形式の催しと組み合わされます。たとえば以下のような構成が代表的です。
- 販売会議+プライベート展示会
全国の販売代理店や営業所責任者を集めて販売方針を伝達し、その場で新商品の展示会を行う。ディーラーミーティングやキックオフ会議がこれにあたる。 - 顧客感謝祭+内覧会
VIP顧客を招いてレセプションパーティを開催し、その合間に自社の新サービスや施設を案内することで商談につなげる。 - 社内表彰・チームビルディング要素の付加
インセンティブ旅行や社員総会と組み合わせ、グループ全体のモチベーション向上を狙うと同時に取引先にも新商品のプレゼンを行う。
このように、コーポレートイベントとしてのプライベート展示会は内向き(社員・組織)と外向き(顧客・取引先)の両方に有効なアプローチをとり、ブランド価値や企業文化を総合的に訴求できる機会となっています。
6.日本国内での実例
日本国内で実際に開催されたプライベート展示会・コーポレートイベントの事例をいくつかご紹介します。
日本ハムグループの合同展示会
大手食品メーカーである日本ハムでは、「ニッポンハムグループ商品・販促説明会」というグループ企業合同のプライベート展示会を開催しています。
- 目的: グループ各社の総合力をPRし、新商品や販促施策をスーパー・コンビニなどの取引先バイヤーに直接提案する。
- 特徴: 毎年、東京・大阪など複数都市で実施し、数千人規模のバイヤーや関係者を招く。試食コーナーや次世代食材、SDGsを意識した取り組みも盛り込まれ、来場者への満足度を高めている。
- 成果: 2025年1月の開催では合計で5500人近い関係者が来場し、大盛況。将来のビジョンやグループ全体の取り組みも紹介することで、取引先の信頼を獲得している。
この事例からは「グループ横断の一体感ある展示」「顧客が実際に体験できる企画」「情報発信(SDGs等)による先見性アピール」といった点が成功を支えていることが伺えます。
トヨタ自動車の「グローバル仕入先総会」
毎年、国内外の主要サプライヤーを集めて開催される会合です。ここでは調達方針や年間目標を共有し、品質向上や原価低減(コスト削減)などの重点施策を発表。質疑応答や懇親の場を通じて、サプライヤーとの協力体制を強化します。一般報道はごく一部に限られますが、「自動車新聞」「日経産業新聞」などが断片的に取り上げ、出席サプライヤー数や大まかな内容が報じられることがあります。
トヨタイムズの記事(2023年の記事) https://toyotatimes.jp/toyota_news/1024.html
クボタの「ディーラーミーティング」
農業機械大手のクボタは、毎年「ディーラーミーティング」と称して全国の販売店や協力企業を集め、新年度の販売方針や新製品紹介を一括して行っています。
- 開催概要: 2025年1月に京都国際会館で開催された「第78回ディーラーミーティング」には、約1,300名が出席。販売会社の拠点長や関連メーカー60社も参加。
- 内容: 社長・役員による講演や優秀販売店の表彰、新機種の展示・デモンストレーション。
- 効果: 全国のディーラー網との一体感を高め、最新商品やメンテナンスサービスを直接訴求することで、販売店側も自社エリアでの販売計画を立てやすくなる。
「販売網への直接コミュニケーション」「表彰によるモチベーション向上」「新製品のリアルな体験機会創出」といった要素が見えてきます。
NTTコミュニケーションズのビジネスフォーラム

情報通信分野では、NTTコミュニケーションズが毎年開催する「docomo business Forum(dbF)」があります。
- 開催規模: 2024年に行われたdbF’24では、2日間で約6500名が来場し、過去最高を記録。
- 展示内容: 生成AI、IoT、セキュリティ、次世代ネットワークなど多岐にわたるICTソリューションを多数展示し、顧客企業は実際にデモ操作を通じてサービスを体感できる。
- イベント設計: 大規模な講演セッションやパネルディスカッションが併催され、参加者は最新事例や業界動向をまとめて収集可能。NTTグループ各社との協業を打ち出すための場でもある。
「業界動向を踏まえた先進ソリューション紹介」「大規模フォーラム形式での知見共有」「ワンストップでの体感型ブース設計」が顧客満足につながり、新規案件開拓と既存顧客との深耕が同時に進むのではないでしょうか。
docomo business Forum’24 https://www.ntt.com/business/go-event.html
アパレル業界のブランド展示会
ファッションブランドの多くは、年2回のシーズン切り替え時にプライベート展示会を開催し、小売店バイヤーやメディア関係者を招待しています。
- 特徴: バイヤー向け受注会を兼ねており、展示会場の世界観やシーズンテーマを重視した空間演出を行う。
- 狙い: ブランドイメージの強化、新規取引先の開拓、バイヤーとの関係性強化、雑誌やSNSでの話題化など。
- 効果: その場でオーダーを確定させるため、商品生産計画や店頭配置スケジュールが早期に確定する。バイヤーが細部まで商品を手に取って見られることで納得感が高まり、発注点数も増える傾向がある。
アパレル展示会では「ブランドのストーリーやムードの共有」「バイヤーに対する受注のしやすさ」「プレス関係者への発信力強化」が重要となります。
7. 今後のトレンドと展望
ハイブリッド形式の進化
新型コロナウイルス感染拡大後、対面とオンラインの併用が一般化しました。プライベート展示会でも遠隔参加できるバーチャルブースやライブ配信が取り入れられ、今後もオンライン連携は拡大すると見込まれます。

事例;オンライン開催 2021年開催「Sony Technology Day」
「感動を生む、テクノロジー」をテーマに8つの技術を紹介。ソニーグループの多様な事業をつなぎ、その進化を支えるテクノロジーについて、「感動を生む、テクノロジー」をテーマに8つの技術を紹介しました。(ソニー プレスリリースより)
特設Webサイト https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/activities/Tech2021/
データ活用・AIの導入
来場者管理や商談履歴、展示会後のフォローアップなどを一元管理し、AIが適切な商談相手や製品提案をマッチングする仕組みが普及しつつあります。
エクスペリエンス重視の演出
製品やサービスの単純展示に留まらず、AR/VRなどの体験型テクノロジーを導入して「記憶に残る」イベントに仕立てる動きが加速しています。
サステナビリティと社会的意義の発信
環境配慮やSDGsへの取り組みをブース設計や展示内容で示し、取引先や顧客に企業姿勢をアピールする事例が増加。省エネや廃棄物削減など、展示会そのものの持続可能性が問われるようになっています。
コミュニティ形成の場としての進化
単なるビジネス交渉・商品の紹介だけでなく、交流スペースやワークショップを設け、参加者同士がつながれるコミュニティ形成の場とする企業も増えてきました。
8. まとめ
企業が行うプライベート展示会や取引先招待型コーポレートイベントは、MICEの枠組みの中でもBtoB取引が中心の日本企業にとって極めて重要なマーケティング・コミュニケーション手段です。クローズド環境であるがゆえにより深い商談や情報共有が可能となり、競合他社のいない状態で自社製品・サービスのアピールを最大化できるメリットがあります。
経営層や上層部を招くことで意思決定のスピードを上げるとともに、ブランドイメージの刷新や企業ビジョンの提示にも有効です。日本ハム、クボタ、NTTコミュニケーションズなどの実例からも分かるように、「ただ見せる」だけでなく、体験・共感・ネットワーキングの場として設計することで大きな効果を生んでいます。
今後はハイブリッド化やデータ利活用による一層の効率化、サステナビリティや社会的価値を組み込んだ開催手法が求められるでしょう。企業はそれぞれの業界特性に合わせて、参加者に「ここでしか得られない体験」と「事後フォロー」を提供することで、ビジネス成果と顧客満足の両立を実現できるはずです。