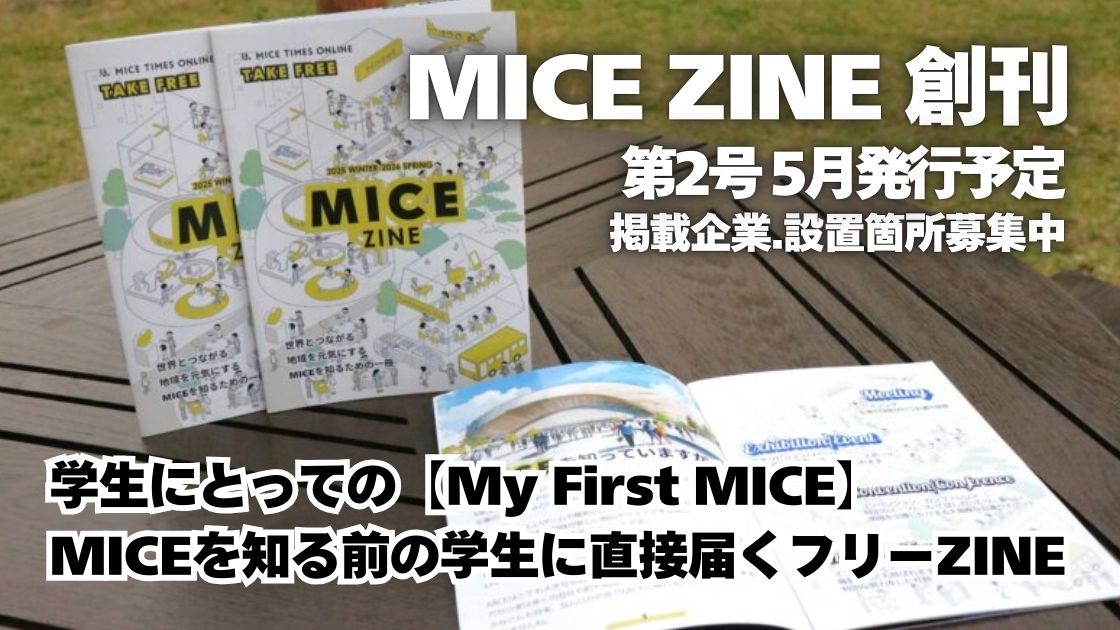「やりたいこと」が見つからなくても大丈夫!自分らしいシゴトを見つける「軸」の育て方【就職活動ガイド】
就職活動を目前に控え、「自分にはやりたいことが何もない」と不安を感じている学生の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その気持ちは決してあなた一人だけが抱えるものではなく、むしろごく自然なことです。現代社会には、多くの学生や若者が「やりたいこと」探しに苦しむ構造的な要因があります。本記事では、漠然としたプレッシャーから解放され、人事のプロも認める「シゴト選びの軸」というコンパスを手に入れる方法をご紹介します。悩みの原因から自己分析、面接での伝え方、そして入社後のキャリア形成まで、あなたの就職活動を力強くサポートします。

やりたいことが見つからないのは当たり前です
学生や若手が抱える「やりたいこと」の悩み
就職活動の時期になると、多くの学生が「やりたいことが見つからない」という壁にぶつかります。在学中に「やりたいことが決まっている」人は全体の約半数にとどまり、卒業まで決めきれない学生も約2割いるのが現状です。この悩みは、個人の意欲や能力の問題ではなく、現代社会が抱える構造的な要因から生まれていることを知っておきましょう。
現代社会では、「好きなことで、生きていく」というメッセージが溢れています。特にSNSや動画プラットフォームでは、個人の情熱を仕事にして輝いている人々の姿が強調され、それが理想的な生き方であるかのような風潮があります。一方で、メディアは会社で働くことのネガティブな側面を頻繁に取り上げがちです。まるで「会社で働くこと」は、やりたいことを見つけられなかった人たちが選ぶ妥協案であるかのようなイメージが植え付けられ、学生に「やりたいことがある」のは素晴らしく、「やりたいことがない自分」は価値がないのではないか、という強迫観念に似た感情を抱かせてしまう側面があります。
SNSがこころの負担になっていることも、人と比べることで過小評価に
また、SNSは、私たちの生活に欠かせないツールとなった一方で、精神的な負担の原因にもなっています。特に就職活動期においては、同世代の友人がインターンシップで活躍する様子や、内定を獲得して喜ぶ投稿などを日常的に目にすることになります。私たちは無意識のうちに、他人の輝かしい1%の姿と、自分の悩みや不安も含めた100%の日常を比較してしまい、「周りは着実に前に進んでいるのに、自分だけが取り残されている」といった自己過小評価に陥りやすくなります。
これまでの学校教育では、決められた正解を効率的に導き出す能力が評価される場面が多く、大きな失敗を経験する機会は少なかったかもしれません。真面目に一つの道を歩み、周囲から「優秀」と見なされてきた人ほど、未知の分野へ一歩踏み出すことに強い恐怖心を抱く傾向があります。さらに、現代は情報過多の時代であり、選択肢が多すぎることで、かえって「どれが自分にとっての正解なのか」が分からなくなり、「決定麻痺」という状態に陥ることがあります。
決定麻痺:選択肢が多すぎることで、選択を先送りにしたり、選択することそのものをやめてしまうことを「決定麻痺」と呼びます。レストランでオーダーするものを迷うくらいならいいのですが、人生の問題となると…決めてしまうことが怖くなることもありますよね
やりたいことはカタログの中にあるとは限らない。自分の体験から生まれてくるもの
そもそも「やりたいこと」とは、本やインターネットで調べてカタログの中から選ぶようなものではありません。
アルバイトでお客様に感謝された経験や、部活動で困難を乗り越えた経験など、何らかの具体的な「原体験」を通じて、自分の中から自然に湧き上がってくるものです。しかし、多くの学生は、授業や部活動、アルバイトといった「やらなければいけないこと」に追われ、多様な世界に触れる経験を十分に積めていないのが実情であり、特にコロナ禍では、価値観を揺さぶるような原体験の機会が大幅に制限されてきました。経験の絶対量が少なければ、何に興味があるのか分からなくて当然なのです。

人事のプロが語る「やりたいこと」の現実
壮大な「やりたいこと」が明確に決まっている学生は、ごく少数派
「やりたいことを熱く語れないと、面接で落とされてしまうのではないか」
多くの学生がそんな不安を抱いていますが、採用担当者の視点は、皆さんが思っているものとは少し違うかもしれません。まず、断言します。就職活動を始める大学3年生や4年生の時点で、人生を懸けて成し遂げたいような壮大な「やりたいこと」が明確に決まっている学生は、ごく少数派です。
私は将来のことを全然決めていませんでした。サラブレッドが好きで毎年、北海道の牧場を訪ねていました。トウカイテイオーやメジロマックイーンなど『ウマ娘』に出てくる馬が現役でした。ゲームも大好きで任天堂の社内を見ることを目的に記念受験したりもしてました。就職したのは当時、大きく成長していたコンビニエンスストアのFC本部。そんな自分が今、MICEのメディアを立ち上げて、若い方に向けてキャリアの記事を書いています。
ポテンシャル採用が広く行われている今の新卒採用の現場
今の日本では新卒採用は、基本的に「ポテンシャル採用」です。これは、現時点でのスキルや経験、明確な目標の有無よりも、入社後にどれだけ成長してくれるかという「伸びしろ」を重視する採用方法を指します。私たちは、完成された「答え」ではなく、あなたがこれまでどのように考え、行動し、学んできたかという「プロセス」を知りたいと考えています。主体性・積極性、学習意欲・素直さ、目標達成意欲、チームワークといった要素が評価ポイントとなります。
人事が面接で「企業選びの軸は何ですか?」と質問するのには、明確な目的があります。
それは、壮大な夢を聞きたいからではありません。主な目的は、大きく分けて二つあります。一つ目は「企業とのマッチ度を見極めるため」、二つ目は「早期離職のリスクを判断するため」です。
したがって、採用担当者の心に響くのは、どこかで聞いたような壮大な夢よりも、自己分析に基づいた明確な「軸」と、それが「なぜこの会社なのか」という志望動機に一貫して繋がっているストーリーなのです。「現時点では、明確にこれだと言える『やりたいこと』はありません」と正直に話す学生に対して、直ちにネガティブな評価を下すことはほとんどありません。むしろ、無理に作り上げたような薄っぺらい夢を語るよりも、誠実さや好感を持つことさえあります。
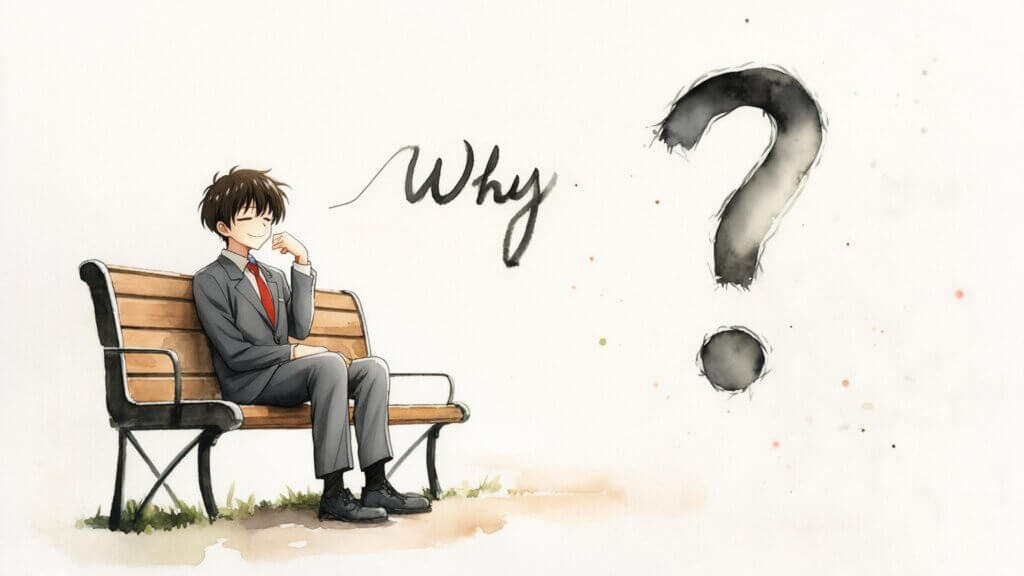
自分だけの「シゴト選びの軸」を見つけましょう
過去の経験を振り返り、自分を知る3ステップ
「シゴト選びの軸」の重要性は分かったけれど、どうやって見つければいいのか分からない、という方も多いでしょう。ここでは、誰でも実践できる具体的な3つのステップを紹介します。
ステップ1:過去の経験を棚卸しする(自己分析)
まずは、これまでの自分の人生を客観的に振り返り、事実を整理することから始めましょう。大切なのは、「就職活動でアピールできそうなすごい経験」を探す必要はない、ということです。部活動、サークル、アルバイト、ゼミ、趣味、友人関係など、どんな些細な出来事でも構いません。
朝から夜まで面接をしていると、それこそバイトリーダーや学生団体の副代表が何人もいて、同じような留学経験とボランティア体験を語る学生ばかりという印象になることがあります。どこかでこういったエピソードが有用だと語られているためでしょうか。他の人と同じ内容だと「(実績が)すごい人」だけが「勝ってしまう」ことになりかねません。
具体的な手法としては、「自分史」と「モチベーショングラフ」がおすすめです。「自分史」は、幼少期から現在まで、印象に残っている出来事を時系列で書き出していく方法です。楽しかったこと、頑張ったことだけでなく、辛かったこと、失敗したこと、悔しかったことなど、ネガティブな感情が動いた経験も正直に書き出してみましょう。困難な状況に直面したとき、自分がどう考え、どう行動したのか。そこに、あなたの強みや価値観のヒントが隠されています。
「モチベーショングラフ」は、横軸に時間(年齢)、縦軸にモチベーションの度合いを取り、人生の出来事ごとにモチベーションの浮き沈みを折れ線グラフで可視化する方法です。グラフの山が高くなっている時や、谷が深くなっている時のできごとに注目します。そして、「なぜその時モチベーションが上がった(下がった)のか?」を考えることで、自分がどんな時にやりがいを感じ、どんな状況を避けたいと思うのか、その傾向を客観的に把握することができます。
昔から行われている方法と言えますが、普遍的なものだとも言えます。自分を主人公にした映画やアニメを作ると考えて、振り返ってみると楽しいです。
ステップ2:「なぜ?」を5回繰り返して自分の価値観を言語化する
ステップ1で洗い出したできごとの中から、特に感情が大きく動いたエピソードをいくつかピックアップします。そして、そのエピソードに対して、「なぜ?」という問いを自分自身に繰り返し投げかけてみましょう。表面的な行動の奥にある、あなたの本質的な動機や価値観を掘り起こすための非常に強力な手法です。
次のように進めます。
エピソード: 「カフェのアルバイトで、お客様に『あなたの接客は気持ちがいいね、ありがとう』と言われて、とても嬉しかった」 なぜ嬉しかったのか?
→ 自分の行動が、直接誰かの役に立ったと実感できたから。
なぜ人の役に立つと嬉しいのか?
→ 誰かが喜んでくれる顔を見ることが、自分の喜びにも繋がるから。
なぜそれが自分の喜びになるのか?
→ 自分が誰かにとって価値のある存在だと感じられるから。
なぜ価値のある存在だと感じたいのか?
→ 他者との繋がりの中に、自分の存在意義を見出したいから。
なぜ繋がりが大切なのか?
→ 一人で何かを成し遂げるよりも、誰かと喜びを分かち合うことに幸せを感じるから。
このように深掘りしていくと、「お客様への感謝」という一つの出来事から、「他者貢献」「人との繋がり」「チームでの協働」といった、あなたが仕事をする上で大切にしたい価値観のキーワードが見えてきます。
ステップ3:「やりたいこと」と「やりたくないこと」から選択肢を絞り込む
自己分析で自分の価値観が見えてきても、すぐに「やりたい仕事」に結びつかないこともあります。そんな時は、発想を転換してみましょう。「やりたいこと」から考えるのではなく、「やりたくないこと」「避けたいこと」から考えてみるのです。
次のようなリストを作ってみます。
毎日同じ場所で、同じ作業を繰り返すのは嫌だ。
成果が見えにくい、縁の下の力持ちだけの仕事は物足りないかもしれない。
個人プレーで評価されるより、チームで協力して達成感を味わいたい。
厳しいノルマに常に追われる環境は避けたい。
「やりたくないこと」を明確にすると、その裏返しとして「やりたいこと」や「自分に合う環境」の輪郭が浮かび上がってきます。上記の例であれば、「変化のある環境」「成果が目に見える仕事」「チームワークを重視する文化」「プロセスも評価してくれる社風」といった軸が見えてくるでしょう。
「Will・Can・Must」というフレームワークで考えるのも有効
Will:やりたいこと、なりたい姿
Can:できること、得意なこと、強み
Must:やるべきこと、求められる役割
「Will」がすぐに見つからない場合は、まず「Can」(自己分析で見つけた自分の強みや得意なこと)をリストアップします。そして、その「Can」を活かせる「Must」(企業や社会から求められている仕事)は何か、という視点で企業を探していくのです。自分の得意なことで貢献できれば、やりがいを感じ、「Will」が後から生まれてくることも少なくありません。
これは将来の転職活動やステップアップを考えるときにも有効なフレームワークです・
仕事選びの軸となる価値観の例
自己分析を通じて見えてきた自分の価値観や傾向を、面接で語れる具体的な「シゴト選びの軸」に落とし込む作業は、一人では難しいかもしれません。ここでは、先輩たちが実際にどのような軸で企業を選んできたのか、豊富な具体例をカテゴリー別に紹介します。これらを参考に、自分にしっくりくる言葉を探してみてください。
「何をするか」で考える軸(事業内容・職種への興味)
仕事の対象や内容そのものに興味がある場合の軸です。自分の行動が社会や人々にどのような影響を与えるかを重視します。 社会貢献性:困っている人を助けたい、人々の生活を便利にしたい、地域社会に貢献したい、地球環境問題の解決に貢献したい。 専門性・技術:専門知識を活かしたい、一生モノの技術を身につけたい、研究開発に携わりたい。 創造性・革新性:自分のアイデアを形にしたい、新しい価値を社会に生み出したい、モノやサービスを作る仕事がしたい。 影響力:多くの人に影響を与える仕事がしたい、日本の文化を海外に伝えたい、社会の問題解決に繋がる仕事がしたい。
「どのように働くか」で考える軸(環境・文化・人)
仕事の内容そのものよりも、働く環境や人間関係、仕事の進め方などを重視する軸です。自分が最もパフォーマンスを発揮できる環境を基準に考えます。 チームワーク・人:チームで一体となって仕事を進めたい、尊敬できる上司や先輩のもとで働きたい、多様な価値観を持つ仲間と働きたい。 社風・文化:風通しが良く、若手の意見も尊重される社風、成果主義で正当に評価される文化、プロセスを重視してくれる文化。 仕事の進め方:自分の裁量で仕事を進めたい、黙々と集中して作業したい、試行錯誤しながら挑戦したい、時間をかけてコツコツと進めたい。
「何を大切にするか」で考える軸(価値観・ワークライフバランス)
仕事とプライベートのバランスや、働く上での根本的な価値観を重視する軸です。人生全体を豊かにするための働き方を考えます。 安定性・継続性:一つの会社で長く働きたい、地元に根ざして働きたい、転居を伴う転勤がない企業がいい。 ワークライフバランス:残業が少なくプライベートの時間も大切にしたい、有給休暇をしっかりと取得できる、育児や介護などライフステージに合わせて柔軟に働ける。 評価・報酬:努力が目に見える形で評価されたい、成果が給与に反映される実力主義の給与体系がいい、福利厚生(住宅補助など)が充実している。
「どうなりたいか」で考える軸(成長・キャリアパス)
仕事を通じて、自分自身がどのように成長し、どのようなキャリアを築いていきたいかを重視する軸です。将来のなりたい姿から逆算して考えます。 成長環境:若いうちから挑戦できる・裁量権のある環境で働きたい、研修制度が充実している企業で学びたい、新規事業の立ち上げに関わりたい。 キャリアアップ:将来の独立に繋がる経験を積みたい、転職市場で価値の高まるスキルを身につけたい、様々な職種を経験してキャリアの幅を広げたい。
これらの軸は、一つだけを選ぶ必要はありません。自分の中で優先順位をつけ、「最も重視するのは成長環境で、次にチームワーク、そしてワークライフバランスも大切にしたい」というように、複数の軸を組み合わせて自分だけの基準を作ることが大切です。

面接で「やりたいこと」を効果的に伝える方法
論理的で説得力のある伝え方
自分だけの「シゴト選びの軸」が見つかったら、最後の仕上げです。面接官に、説得力を持って魅力的に伝えるための具体的な方法を学びましょう。自己分析の成果を最大限に活かすためのコミュニケーション技術です。
結論から話すPREP法が基本のキ
面接官は、多くの学生と限られた時間の中で面接をしています。話が分かりやすく、論理的であることが非常に重要です。そこで役立つのが「PREP法」というフレームワークです。
P(Point):結論(私のシゴト選びの軸は〇〇です)
R(Reason):理由(なぜなら、△△という経験から□□だと考えるようになったからです)
E(Example):具体例(具体的には、大学時代の〇〇という活動で…)
P(Point):結論の再確認(したがって、私は〇〇という軸で企業を選んでいます)
まず「私のシゴト選びの軸は、チームで協力して目標を達成できる環境です」と結論を簡潔に述べることで、面接官は話のゴールを理解し、その後の話に集中しやすくなります。だらだらとエピソードから話し始めるのではなく、結論から入ることを徹底しましょう。
具体的なエピソードで圧倒的な説得力を持たせる
「シゴト選びの軸」そのものに、優劣はありません。重要なのは、「なぜあなたがその軸を大切にしているのか」という背景です。その背景に説得力を持たせる唯一の方法が、あなた自身の具体的なエピソードです。「成長できる環境が軸です」とだけ伝えても、他の多くの学生と同じで印象に残りません。抽象的で、入社意欲が低いと判断される可能性すらあります。そうではなく、自己分析で見つけたエピソードと結びつけましょう。
その企業ならではの魅力と自分の軸を結びつける
最後の、そして最も重要なステップは、あなたの軸と、「なぜ、他の会社ではなく、この会社なのか」を結びつけることです。これができなければ、「その軸なら、うちの会社じゃなくてもいいですよね?」と面接官に思われてしまいます。そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。その企業のウェブサイト、説明会、OB・OG訪問などを通じて、事業内容、企業理念、社風、独自の制度など、他社にはない魅力を見つけ出します。そして、その企業独自の特徴と、自分の軸がどのように合致しているのかを、具体的に言語化するのです。ここまで具体的に語ることができれば、あなたの志望度の高さと、企業とのマッチ度の高さが明確に伝わり、面接官に「この学生は、自社で活躍してくれそうだ」という強い印象を残すことができるでしょう。
「働き方の姿勢」と「合う環境」をアピールする
就職活動の面接で「入社後にやりたいことは何ですか?」と質問されたとき、明確な職種や夢がない場合でも落ち込む必要はありません。その代わりに、自分の仕事選びの軸や働く上での姿勢を伝えるようにしましょう。企業が本当に知りたいのは、あなたの具体的な目標というより「価値観や軸が自社と合っているかどうか」だからです。
「具体的なやりたいことは探索中ですが、こういう価値観で、こう働きたい」という姿勢を軸で語り、なぜその企業の環境と合うと考えるかを補います。「社会課題に共感しなければならない」といった思い込みは根強いですが、それ自体が正解ではありません。あなたが仕事で大切にしたい価値(例えば成長機会、協働、安定、裁量など)を正直に語る方が、入社後のミスマッチを防ぎます。
「合いすぎ」に注意し、多様性を受け入れる
個人と組織文化の適合が高いほど、満足や愛着は高まり、離職意向は下がる傾向が確認されています。しかし、組織全体で“合いすぎ”ると多様性の低下につながり、変化対応力や革新性を損なう恐れがあります。個人としては「土台の価値観は合うか」を見つつ、「異質さから学べるか」も合わせて軸に含めると、成長の幅が広がります。
まとめ: 「やりたいことが見つからない」という悩みは、決してあなたの欠点ではありません
むしろ、情報が溢れ、多様な価値観が交錯する現代において、自分自身と真剣に向き合おうとしている証拠です。就職活動は、完璧な「答え」を見つけるための試験ではありません。この記事で紹介した「シゴト選びの軸」という考え方は、不確実な未来の海を航海するための、あなただけの「羅針盤」なのです。
羅針盤があれば、たとえ将来「やりたいこと」が変わったとしても、その時々で自分らしい選択をしていくことができます。自己分析は、一度行ったら終わりというものではありません。就職活動を進める中で、様々な企業や社会人と出会い、新たな自分に気づくこともあるでしょう。社会人になってからも、経験を積むことで価値観は変化していきます。
焦らず、悩みながら、自分だけの軸を少しずつ磨き上げていってください。そのプロセスそのものが、あなたを成長させ、納得のいくキャリアへと導いてくれるはずです。