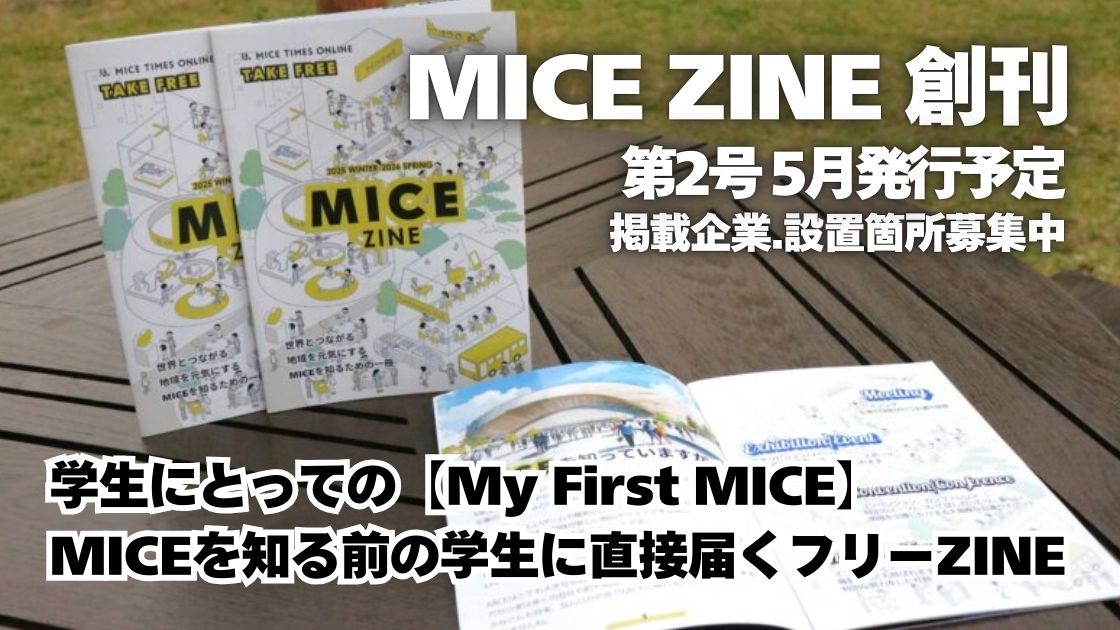小手先の準備では対応できない、コンピテンシー面接の対策完全ガイド|学生必見!STAR法で差をつける就活・行動面接攻略術【MICEキャリアナビ】
私は企業の採用担当者として、他社の人事を支援する立場として、そして今は自社の経営者として、毎日のように「面接」を行っていきました。人材紹介会社の役員としてキャリア面談も数多く担当しました。その数は2,000名以上、30分~1時間に渡る個人面接がほとんどです。
面接が得意な方というのはほとんどいません。「選ばれる」「慣れていない」ことから緊張と焦りで失敗したと感じることが多いでしょう。いくら売り手市場でも、面接を受けるほうが緊張するのは当然です。面接には絶対的な必勝法はなく、担当者との相性や他の応募者の経歴など自分ではコントロールできない部分もあります。しかし、準備をすることは可能です。
今回はなかでも対策が難しい「コンピテンシー面接」についてお伝えします。プロの人事・採用担当は面接の「プロフェッショナル」でもあります。小手先のエピソードトークは通用しません。人事が何のためにどのような面接をしているのかを知ることで、正しい対策ができるようになります。

まずはコンピテンシー面接を理解しよう。評価基準が明確な誰にでもチャンスがある選考方法
多くの企業が採用活動に取り入れているコンピテンシー面接。名前は聞いたことがあっても、「一体何を準備すればいいの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、安心してください。この面接は、評価基準が明確で、準備さえすれば誰にでもチャンスがある、実は学生にとって非常に有利な選考方法なのです。
私も面接担当者として、数日間の研修を受けて面接技術を学びました。プロの人事担当者は、面接のための技術や知識を身につけることで、企業にとって非常に重要な採用活動の成功に備えています。企業も採用活動に本気であるということです。応募者であるあなたも本気で準備をしなければいけないということですね。
この記事を最後まで読めば、コンピテンシー面接の本質を理解し、自信を持って本番に臨めるようになります。心強いの武器となる「STAR法」を使いこなし、ライバルに差をつけましょう。
コンピテンシー面接を理解する:行動面接との違いと最新トレンド
まずは、コンピテンシー面接がどのようなものか、その全体像を正しく理解することから始めましょう。なぜ企業がこの方法を導入しているのか、その背景を知ることで、面接官の意図を深く読み解くことができるようになります。
コンピテンシー面接は「過去の具体的な行動」からコンピテンシーを見極める手法
コンピテンシー面接とは、あなたの「過去の具体的な行動」に焦点を当て、そこから「将来、企業で活躍できる力(コンピテンシー)」があるかどうかを見極めるための面接手法です。面接官が知りたいのは、学歴やアルバイト経験の有無といった表面的な情報ではありません。「ある状況で、あなたが何を考え、どのように行動し、結果として何を生み出したのか」という一連のプロセスです。
この面接の根底には、「過去の行動パターンは、将来の行動を予測する最も確かな指標である」という考え方があります。企業は、自社で高い成果を上げている社員(ハイパフォーマー)の行動特性を分析し、その「成功の秘訣」となる能力をコンピテンシーとして定義しています。そして面接では、あなたがそのコンピテンシーに近い行動特性を持っているかを、具体的なエピソードを通して確認しようとします。
そのため、第一印象や流暢な自己PRよりも、事実に基づいた具体的なエピソードが何よりも重要になります。まだ社会人経験のない学生の皆さんにとって、サークル活動やゼミ、アルバイトといった経験から、自分のポテンシャルを存分にアピールできるチャンスなのです。
表1:従来型面接 vs. コンピテンシー面接
| 評価項目 | 従来型面接 | コンピテンシー面接 |
| 主な質問 | 志望動機、自己PR、長所・短所など、あなたの「考え」や「意見」を問う質問 | 「〜した時、どうしましたか?」など、あなたの「過去の具体的な行動」を問う質問 |
| 評価の基準 | 面接官の主観や印象、価値観との相性 | 企業が定めた明確な評価基準(コンピテンシー) |
| 見ているもの | 人柄、熱意、コミュニケーション能力の印象 | 成果に繋がる行動特性、思考のプロセス、課題解決能力 |
| 応募者への影響 | 印象や話し方、企業の求める人物像に合わせる能力が重要 | 具体的なエピソードの説得力、自己分析の深さが重要 |
行動面接・STAR面接との共通点と相違点
就職活動を進めていると、「行動面接」や「STAR面接」といった言葉も耳にするかもしれません。これらの言葉はコンピテンシー面接と密接に関連しており、混同しやすいため、整理しておきましょう。結論から言うと、これらは別物ではなく、大きな枠組みの中に含まれる関係です。
まず、「行動面接(ビヘイビア面接)」とは、過去の行動について質問する面接スタイルの総称です。「〜という経験はありますか?」といった質問を受けたことはありませんか。
そして「コンピテンシー面接」は、この行動面接の一種です。ただし、単に行動を問うだけでなく、企業が事前に定めた「コンピテンシー(活躍する人材の行動特性・行動原理)」を評価する、という明確な目的を持っています。つまり、より構造化され、評価基準がはっきりしているのが特徴です。
「STAR面接」は、面接の種類ではなく、これらの面接で効果的に受け答えをするための「フレームワーク(思考の型)」を指します。状況(Situation)、課題(Task)、行動(Action)、結果(Result)の頭文字を取ったもので、この順番でエピソードを語ることで、誰が聞いても分かりやすく、説得力のある説明が可能になります。
料理に例えるなら、「行動面接」が「イタリア料理」というジャンル、「コンピテンシー面接」が「カルボナーラ」という特定の料理、そして「STAR法」は、そのカルボナーラを美味しく作るための「レシピ」と言えるでしょう。このレシピさえマスターすれば、どんな面接にも対応できるのです。
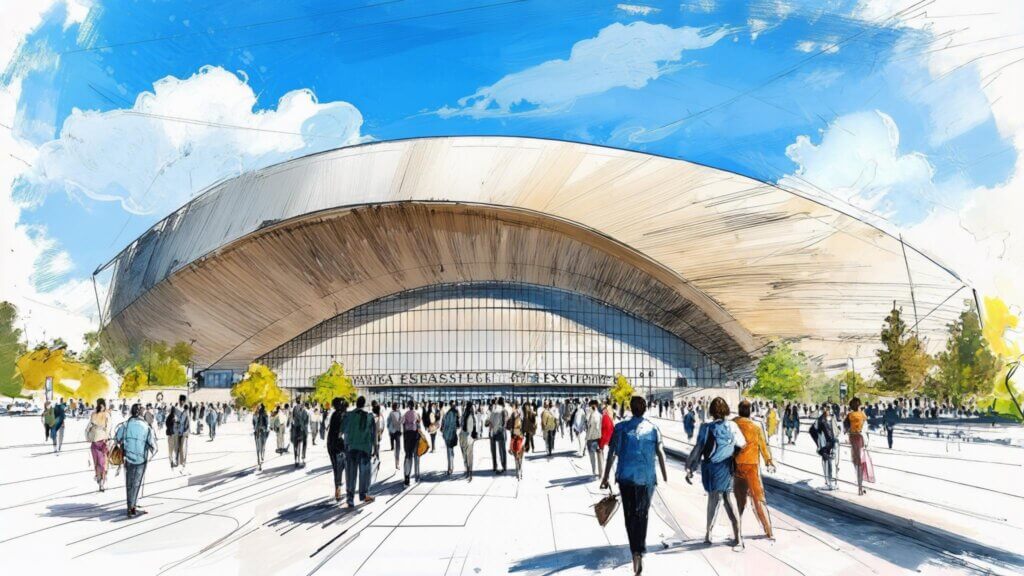
企業が評価する主なコンピテンシー5つを解説
企業や職種によって求められるコンピテンシーは異なりますが、多くの企業で共通して重視される普遍的な能力が存在します。皆さんの学生生活の中にも、これらの能力を発揮した経験は必ず隠れています。ここでは、特に重要な5つのコンピテンシーを紹介します。自分の経験を振り返る際の「レンズ」として活用してみてください。
- 主体性:実行力指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決のために行動を起こす力です。誰も気づかなかった問題点を指摘したり、新しい取り組みを提案したりした経験です。
- 課題解決能力:複雑な状況を整理し、問題の本質を突き止め、解決策を論理的に導き出す力です。研究で行き詰まった原因を分析したり、アルバイト先での非効率な作業手順を改善したりした経験が当てはまります。
- チームワーク・協調性:多様な価値観を持つ人々と協力し、一つの目標に向かって進む力です。サークル活動での役割分担や、意見が対立した際の調整役、グループワークでの議論への貢献などが良い例です。
- 粘り強さ・ストレス耐性:困難な状況でも諦めずに最後までやり遂げる力、そして失敗から学び、次へと活かす力です。高い目標を掲げて努力を続けた経験や、予期せぬトラブルに対応した経験などが該当します。
- リーダーシップ:正式な役職の有無にかかわらず、周囲の人々を巻き込み、目標達成へと導く力です。チームの士気を高めるために働きかけたり、後輩の指導やサポートを率先して行ったりした経験がアピール材料になります。
表2:学生生活で見つける主要5コンピテンシー
| コンピテンシー | 簡単に言うと | こんな経験で発揮! |
| 主体性・実行力 | 自ら考え、 行動を起こす力 | ・サークルでの新企画立案・アルバイト先での業務改善提案 ・誰もやりたがらない役割への立候補 |
| 課題解決能力 | 問題の原因を分析し、 解決策を考える力 | ・ゼミ研究での壁の乗り越え ・非効率な作業プロセスの改善 ・イベントでのトラブルやアクシデントへの対応 |
| チームワーク・協調性 | 周囲と協力して目標を達成する力 | ・チーム作業での意見調整 ・サークル活動での役割分担 ・アルバイトでの新人教育・サポート |
| 粘り強さ・ストレス耐性 | 困難を乗り越え、やり遂げる力 | ・高い目標(資格取得、大会出場など)への挑戦 ・長期間続けたアルバイトや学業 ・失敗からの学びと再挑戦 |
| リーダーシップ | 周囲を巻き込み、目標へ導く力 | ・チームのまとめ役、部長 ・リーダー経験・後輩への指導やアドバイス ・目標達成のためのメンバーへの働きかけ |
2025年最新データで見る導入率と採用トレンド。AIによる評価にも活用される可能性もある
「2025年卒の採用で、コンピテンシー面接はどれくらい実施されるのか?」という点は、皆さんが最も気になるところでしょう。具体的な導入率の公式データはありませんが、この面接手法が今後ますます主流になることは間違いありません。
その背景には、日本の労働人口の減少という深刻な課題があります。かつてのように「大量に採用し、その中から優秀な人材が育てば良い」という考え方は、もはや通用しません。企業は1~2回の面接による採用で、自社に本当にマッチし、長く活躍してくれる人材を確実に見極める必要に迫られています。コンピテンシー面接は、面接官の主観や勘に頼らず、客観的な基準で候補者の能力を測れるため、「採用精度の向上」というニーズに合致しているのです。
また、GoogleやAmazonといった世界的な企業がこの手法で成功を収めていることも、導入を後押ししています。さらに将来的には、AIによる採用選考の活用が進むと考えられますが、AIが候補者を正しく評価するためには、構造化された一貫性のあるデータが必要です。コンピテンシー面接で得られる具体的な行動データは、まさにAIの学習に最適であり、この流れは今後も加速していくでしょう。
したがって、コンピテンシー面接の対策をすることは、単なる就活テクニックではなく、これからのキャリアでずっと役立つ普遍的なスキルを磨くことにもつながることでしょう。
就活生に有利な理由:評価基準の“見える化”効果
コンピテンシー面接は、企業側だけでなく、実は学生の皆さんにとっても多くのメリットがある、非常に公平な選考方法です。 人によっては威圧的で答えづらいことを聞かれているようにに感じるかもしれませんが、むしろ歓迎すべき変化だと捉えましょう。
最大のメリットは、評価基準が「見える化」されることです。従来の面接では、「何が評価されるか分からない」という不安がつきものでした。しかし、コンピテンシー面接では、企業が求める能力(コンピテンシー)が明確です。皆さんは「何をアピールすれば良いか」を理解した上で、戦略的に準備を進めることができます。闇雲に努力するのではなく、ゴールに向かって的確に準備できることを意味します。
企業がどのようなコンピテンシーを求めているかは、実際に活躍されている社員の方のコンピテンシーを知ることで見えてくるとも言えます。ネットや学生の間での噂話よりも、あなた自身が知ることで確認できる確かなものと言えます。
また、この面接は非常に公平です。面接官の個人的な好みや、大学名、見た目といった表面的な要素に評価が左右されにくくなります 。評価の土台となるのは、あくまで皆さんが語る「具体的な行動の事実」です。つまり、どんな経験であっても、そこから学び、主体的に行動した経験があれば、誰にでも平等に評価されるチャンスがあります。自分の努力や工夫を、ありのままに伝えれば良いのです。企業とのミスマッチが減り、入社後も「自分らしく活躍できる」可能性が高まります。
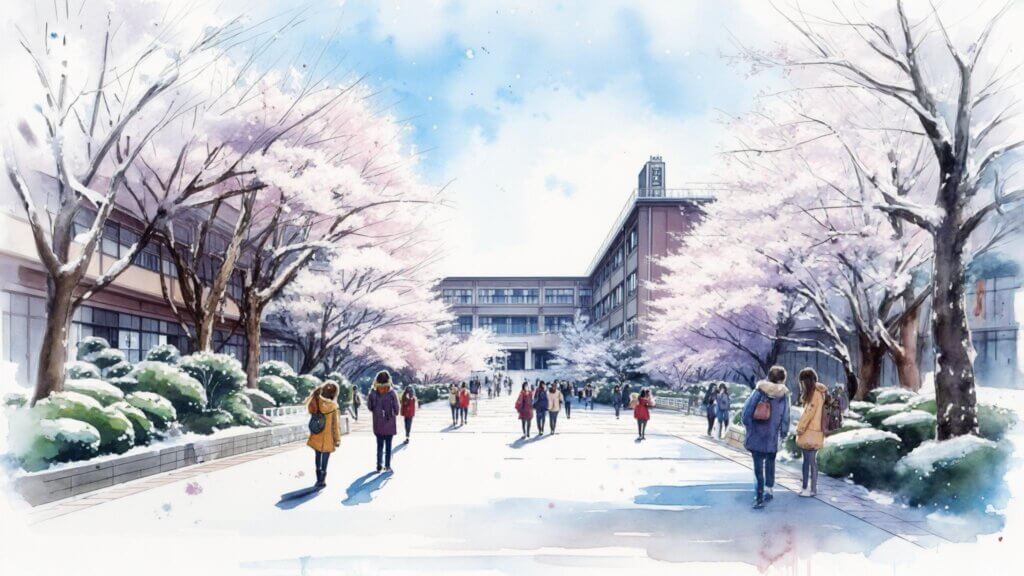
【準備編】STAR法でつくるコンピテンシー面接対策エピソード
コンピテンシー面接の構造を理解したら、次はいよいよ面接で語る「エピソード」の準備です。最強の武器となる「STAR法」を使い、あなたの経験を面接官に響く魅力的なストーリーに変える方法を、順番に解説します。
求人票リバースエンジニアリングで求めるスキルを特定
最強のエピソード作りは、まず「相手を知る」ことから始まります。そのための最も重要な資料が、企業の「採用ホームページ」「求人票」や「募集要項」です。これを単なる仕事内容のリストとして読むのではなく、「企業からのメッセージ」として読み解き、求められているスキルを逆算する、いわば「リバースエンジニアリング」を行うのです。
注目すべきは、「業務内容」「求める人物像」「募集背景」の3つのセクションです。ここに繰り返し登場する言葉は、企業が最も重視しているコンピテンシーのヒントです。「新規事業の立ち上げ」「チームで連携し」といった言葉があれば、「主体性」や「チームワーク」が求められていると推測できます。「既存業務の効率化」とあれば、「課題解決能力」が重要視されているかもしれません 。
特に「募集背景」は重要です。「事業拡大に伴う増員」であれば、新しいことに挑戦する意欲や行動力が求められるでしょう。一方で「欠員補充」であれば、既存のチームにスムーズに溶け込み、着実に業務を遂行する協調性や堅実さが評価される可能性があります。新卒募集の場合はそんなものは書いていないじゃないかと思われるかもしれません。しかし、ここ数年の採用人数、募集職種から募集背景は見えてきます。将来の海外展開をにらんで語学力を重視する傾向が見えるかもしれないです。
先輩社員情報も必見です。数多くの社員から企業を代表して紹介しているということは、「こんな人にもっと来てほしい」というニーズそのものだと受け取ることができます。
このように求人票を深く読み込むことで、「この企業はこの面接で、特に〇〇と△△の能力を確認したいのだろう」という仮説を立てることができます。その仮説に基づいて、自分の数ある経験の中から最も響くエピソードを選択することが、内定への近道となるのです。
自己分析 → STARシート作成テンプレート
企業が求めるスキルを特定したら、次は自分の経験の棚卸しです。ここで役立つのが、あなたの経験を「最強のエピソード」に構造化するためのツール、「STARシート」です。
まずは、エピソードの材料探しから始めましょう。手帳やSNSの投稿を読み返したり、友人や家族に「私が何かに夢中になっているように見えた時ってどんな時?」と聞いてみたりするのも有効です。また、これまでの人生を時系列で書き出す「自分史」を作成してみるのも良い方法です。楽しかったこと、苦労したこと、夢中になったことを書き出す中で、アピールできる経験の原石が見つかるはずです。
エピソードの原石が見つかったら、以下のSTARフレームワークに沿って整理していきます。これがSTARシートの作成です。
- S (Situation):状況その出来事が「いつ、どこで、誰と」起きたのかを簡潔に説明します。背景をイメージさせるための、物語の導入部分です。
- T (Task):課題・目標その状況で、あなたが果たすべき役割や、達成すべき目標、解決すべき課題は何だったのかを具体的に記述します。
- A (Action):行動課題解決や目標達成のために、「あなた自身が」具体的に何をしたのかを記述します。エピソードの核となる最も重要な部分です。なぜその行動を選んだのか、どんな工夫をしたのかを詳しく書きましょう。
- R (Result):結果あなたの行動によって、どのような結果が生まれたのかを客観的に示します。可能であれば数字を用いて定量的に表現すると、説得力が格段に増します。そして、その経験から何を学んだのかも付け加えましょう。
このシートをいくつか作成しておくことで、面接でどんな質問が来ても、引き出しから最適なエピソードを取り出して話せるようになります。
表3:最強エピソードを作るSTARシート
| フレームワーク | ガイドとなる質問 | 記入例(カフェのアルバイト) |
| S (Situation)状況 | いつ、どこで、どのような状況でしたか? チームの構成やあなたの立場は? | 私がアルバイトリーダーを務めていたカフェでは、 新人スタッフの定着率が低く、常に人手不足の状態でした。 |
| T (Task)課題・目標 | あなたの具体的な役割や目標は何でしたか? どんな課題がありましたか? | そこで私は、新人教育の仕組みを改善し、 「3ヶ月以内の離職率を50%改善する」という目標を立てました。 |
| A (Action)行動 | 目標達成のために、具体的に「あなた」が考え、行動したことは何ですか? なぜその行動を選びましたか? | 具体的に3つの施策を実行しました。 ・業務マニュアルを図やイラストで補足し、 視覚的に分かりやすくしました。 ・先輩が1対1で指導するメンター制度を店長に提案し、導入しました。 ・週に1度、新人スタッフと30分の面談時間を設け、 不安や疑問を解消する場を作りました。 |
| R (Result)結果 | あなたの行動の結果、何が起こりましたか?(数字で示す) その経験から何を学びましたか? | 結果、3ヶ月後の離職率は導入前の40%から10%まで低下し、 店舗全体のサービス品質も安定しました。 この経験から、課題を特定し、周囲を巻き込みながら具体的な計画を立てて実行する重要性を学びました。 |

アルバイト・ゼミ・ガクチカを強みエピソードに変えるコツ
「サークルで部長をしていたわけでもないし、特別な実績もない…」と不安に思う必要は全くありません。面接官が見ているのは、経験の規模や華やかさではなく、その経験を通じてあなたがどのように考え、行動したかという「プロセス」です。ありふれた経験でも、以下のコツを押さえれば、十分に魅力的な強みエピソードに変わります。
- 「なぜ?」を深掘りする「〇〇をしました」という事実だけでなく、「なぜそうしようと思ったのか?」という動機や目的を語りましょう。例えば、「マニュアルを作成した」だけでなく、「新人スタッフが同じミスを繰り返しており、その原因が口頭での説明だけにあると考えたため、誰が見ても分かるマニュアルが必要だと思いました」と説明することで、あなたの課題発見力や思考プロセスが伝わります。
- 数字で語る説得力を高める最も簡単な方法が、数字を用いることです。「売上が上がった」ではなく、「担当商品の売上が前月比で15%増加した」。「多くの人が参加した」ではなく、「5つの大学から約100名が参加したイベントを企画した」のように、具体的な数字を入れることで、エピソードの解像度と信頼性が一気に高まります。
- 「私」を主語にするゼミやサークル活動など、チームでの経験を語る際は、「私たちは〜」ではなく、「私は〜という役割で、〜をしました」と、自分の具体的な貢献を明確にしましょう。チームの中であなたがどのような価値を発揮したのかを伝えることが重要です。
- 学びを言語化するすべてのエピソードの締めくくりとして、「この経験から〇〇を学びました。この学びは、貴社での△△という業務で活かせると考えています」と、経験から得た教訓と、それを入社後にどう活かすかを述べましょう。これにより、あなたが経験を次に繋げる学習能力の高い人材であることがアピールできます。
質問例&回答例:自己PR・ガクチカのOK/NG比較
エントリーシートや面接で必ずと言っていいほど聞かれる「自己PR」と「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」。この二つは似ているようで、実は面接官が知りたいポイントが少し異なります。この違いを理解し、同じエピソードでも角度を変えてアピールするテクニックを身につけましょう。
まず、質問の意図の違いです。
「自己PR」は「あなたの強みは何ですか?」という問いであり、あなたの「能力(スキル)」に焦点が当たっています。
一方、「ガクチカ」は「あなたは何に打ち込みましたか?」という問いで、目標達成までの「プロセス(過程)」に興味を持っています。
しかし、心配する必要はありません。一つの強力なエピソードがあれば、両方の質問に対応可能です。一つのエピソードから、複数の使い方をすればいいのです。例えば、自己PRでは「私の強みは課題解決能力です」とスキルを結論として先に述べ、その証拠としてエピソードを簡潔に話します。ガクチカでは、「カフェのアルバイトで新人教育の改善に力を入れました」と経験から話し始め、その過程で課題解決能力が発揮されたことを物語として詳しく語るのです。
この違いを、以下のOK/NG比較で具体的に見てみましょう。
表4:STAR法を使った回答のOK/NG比較
| 質問 | NG例(抽象的で伝わらない) | OK例(STAR法で具体的・論理的) |
| 「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?」 | はい、飲食店のアルバイトです。チームワークを大切にしながら、 お店の売上向上に貢献できるよう一生懸命頑張りました。 大変なこともありましたが、周りの仲間と協力することで乗り越えられ、大きなやりがいを感じました。 | はい、私が学生時代に最も力を入れたのは、カフェのアルバイトにおける新人教育の改善です。 (S)状況: 当時、私がリーダーを務める店舗では、新人スタッフの定着率が低く、常に人手不足の状態でした。 (T)課題: そこで私は、教育体制を見直し「3ヶ月以内の離職率を50%改善する」という具体的な目標を設定しました。 (A)行動: 目標達成のため、業務マニュアルの図解化、メンター制度の導入、週1回の面談の実施という3つの施策を自ら企画し、店長や他のスタッフを巻き込みながら実行しました。 (R)結果: 結果として、3ヶ月後の離職率は20%まで低下し、店舗全体のサービスが安定しました。この経験から、課題の本質を捉え、具体的な計画を立てて周囲と協力しながら実行する重要性を学びました。 |
失敗談の組み立て方:リカバリー思考を示すフレームワーク
面接で最も答えにくい質問の一つが「あなたの失敗談を教えてください」でしょう。しかし、これはあなたを落とすための意地悪な質問ではありません。むしろ、あなたの誠実さ、自己分析能力、そして困難から立ち直る力(レジリエンス)といった、非常に重要なコンピテンシーを見るための絶好の機会なのです。
失敗談を語る際は、単に失敗した事実を話すのではなく、「失敗から何を学び、どう成長したか」を伝えることが重要です。以下の「失敗から成長へ」のフレームワークに沿って、話を組み立ててみましょう。
- 状況と失敗の共有まず、「いつ、どこで、どのような失敗をしたのか」を正直かつ簡潔に説明します。言い訳をせず、自分の責任として事実を認めましょう。
- 原因の分析次に、「なぜその失敗が起きたのか」自分なりに分析した内容を伝えます。「準備不足だった」「自分の思い込みで判断してしまった」「周囲との連携が不足していた」など、客観的な原因分析は、あなたの論理的思考力を示します。
- 具体的な対応とリカバリー失敗を放置せず、状況を改善するために「具体的にどのような行動を取ったか」を説明します。ミスをどのようにカバーしたか、関係者にどう謝罪し、説明したかなど、責任感のある行動を示すことが大切です。
- 学びと今後の活用最後に、そして最も重要な部分です。「その失敗経験から何を学び、その教訓を今後どのように活かしていくか」を明確に述べます。この部分で、あなたが失敗を成長の糧にできる、前向きな人材であることを強くアピールできます。
避けるべきは、「頑張りすぎて体調を崩した」といった自慢に聞こえかねない話や、他責にするような話です。誠実に自分と向き合った経験を選び、成長の物語として語りましょう。
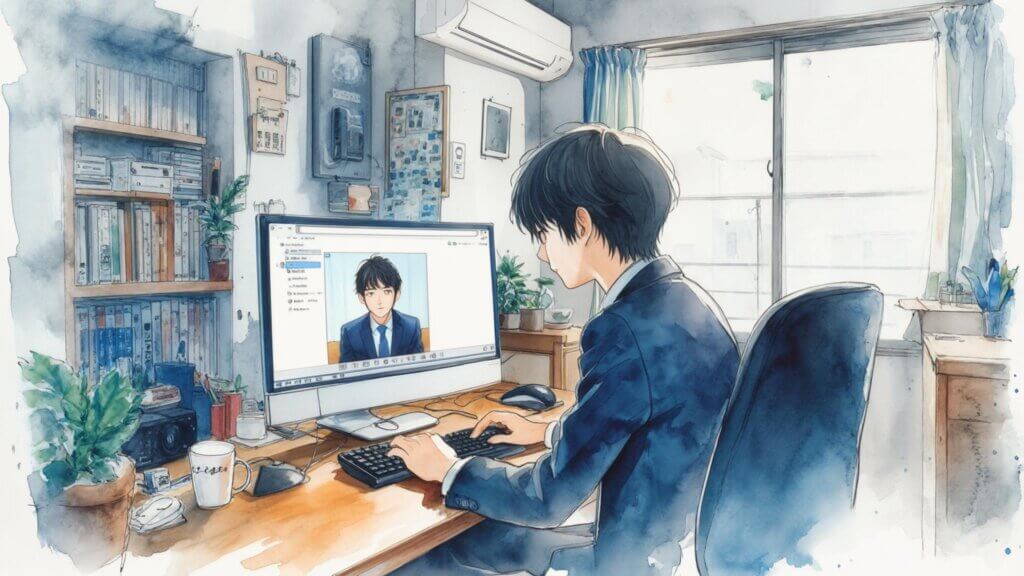
【本番編】オンライン・対面で差をつける面接テクニック
入念な準備を終えたら、いよいよ本番です。面接当日にあなたの魅力を最大限に引き出すための、具体的な会話のテクニックや、オンライン面接特有の注意点について解説します。
STAR法質問リストと掘り下げ質問への切り返し
コンピテンシー面接では、評価したい能力に応じて、ある程度典型的な質問が用意されています。例えば、「チームワーク」を見たい場合は「意見が対立した経験はありますか?」、「課題解決能力」を見たい場合は「最も困難だった課題をどう乗り越えましたか?」といった質問です。
しかし、重要なのは最初の回答だけではありません。面接官はあなたのSTARストーリーを聞いた後、必ず「深掘り質問」をしてきます。「なぜその行動が最善だと思ったのですか?」「他にどんな選択肢を検討しましたか?」「その時、周りの反応はどうでしたか?」といった質問です。
この深掘り質問こそが、あなたの思考の深さや人柄が本当に試される場面です。面接官があなたの話に興味を持っている証拠です。むしろ、「待ってました」「自分に興味をもってくれている」と歓迎するくらいの気持ちで臨みましょう。
対策としては、準備したSTARシートの各項目に対して、自分で「なぜ?」と問いかけてみることです。「なぜその目標を立てたのか?」「なぜその行動を選んだのか?」「もし今同じ状況なら、もっとうまくやるためにどうするか?」といった問いの答えを考えておくだけで、深掘り質問にも落ち着いて、より具体的に答えることができるようになります。面接は尋問ではなく、対話なのです。
面接官の立場で書類を見れば、どのような質問をしたくなるか見えてくるような、コンピテンシー面接は決して怖くありません。
数字と比較で説得力を上げる話し方:結論を先に+定量化
面接での話し方一つで、あなたの印象は大きく変わります。特に、論理的で説得力のあるコミュニケーション能力を示すために、「結論ファースト」と「定量化」の2つを意識しましょう。
まず、「結論ファースト」は、質問に対して「私の強みは〇〇です」「理由は△△だからです」というように、結論から話し始める手法です。PREP法(Point→Reason→Example→Point)とも呼ばれ、聞き手である面接官が話の全体像をすぐに理解できるため、非常に分かりやすい印象を与えます。数多くの面接を担当する面接官への配慮にもなり、論理的思考力の高さをアピールできます。
次に、「定量化」、つまり数字を使って話すことです。これはあなたの話に客観性と信頼性、具体性を与える強力な武器です。「頑張りました」ではなく「毎日3時間勉強しました」。「改善しました」ではなく「作業時間を10%短縮しました」。このように具体的な数字を盛り込むことで、あなたの行動のインパクトが明確に伝わります。
もし数字で示しにくい場合は、「店長から『君のおかげでクレームが半分になったよ』と言われました」といった第三者からの評価や、「前期と比べて、格段にスムーズに進行できました」といった比較表現を使うのも効果的です。
オンライン面接対策:カメラ・音質・視線の最適化
今や主流となったオンライン面接。対面とは異なる準備が必要です。ここでの目標はただ一つ、「技術的な問題であなたの評価を下げさせない」ことです。面接官があなたの話に100%集中できる環境を整えましょう。
インターネットの回線が安定していること、機材やアプリに慣れておくことも大切です。
映像(カメラと光)
カメラは必ず目線の高さに設置しましょう。PCを机に置いたままだと、見下ろす角度になり、偉そうな印象を与えかねません。本などを積んで高さを調整してください。背景は白い壁など、シンプルで物が少ない場所を選びましょう。生活感が出ると面接に集中してもらえません。また、照明は非常に重要です。窓など、光源に向かって座るのが基本です。部屋が暗い場合は、デスクライトを使ったり、机に白い紙を置いたりして顔を明るく照らしましょう。
私が経験したものでは、暗くて表情が見えない、角度がおかしくて顔がよく見えない(天井ばかり見える)といったことがあります。
音声(マイクと環境)
PC内蔵のマイクは生活音を拾いやすいため、マイク付きのイヤホンやヘッドセットの使用を強く推奨します。これにより、自分の声がクリアに届き、相手の声も聞き取りやすくなります。事前に友人などと通話テストをして、音声品質を確認しておくと万全です。
視線(アイコンタクト)
これがオンライン面接で最も重要かつ、多くの人が間違えるポイントです。話すときは、画面に映る面接官の顔ではなく、「カメラのレンズ」を見てください。そうすることで、相手にはあなたとしっかり目が合っているように見え、熱意や自信が伝わります。カメラの横に「ここを見る!」と書いた付箋を貼っておくのも良い方法です。
またスマホやメモを見ているのか?と気になる方も実際にいます。オンラインでの実施だから起こることを想定しておきましょう。
表5:オンライン面接チェックリスト
| チェック項目 | 最適な状態 | やってみよう! |
| 環境 | 静かで、背景に余計なものが映らない場所 | ・家族に面接時間を伝えておく ・無地の壁を背景にする |
| 映像 | 顔が明るくはっきりと映り、目線と同じ高さにカメラがある | ・窓に向かって座る ・本でPCの高さを調整する |
| 音声 | 自分の声がクリアに聞こえ、雑音が入らない | ・マイク付きイヤホンを使用する ・友人との通話テストで確認する |
| 視線 | 話すときはカメラのレンズを見つめ、アイコンタクトを取る | ・カメラの横に目印の付箋を貼る ・スマホは見えないところにしまう (思わず見てしまうのを防ぐ) |

逆質問で印象UP:面接官がうれしい質問例とNG質問
面接の最後に必ず設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間。「やっと終わる」と安堵する時間にしてはいけません。あなたが企業への熱意や理解度をアピールできる最後の、そして絶好のチャンスです。
良い逆質問は、あなたの入社意欲や、企業研究の深さを示します。以下のようなカテゴリーで、いくつか質問を準備しておきましょう。
- 入社後の活躍に関する質問「入社後、一日も早く貴社に貢献するために、今のうちから勉強しておくべき知識やスキルはありますか?」
- 事業や仕事内容に関する質問「本日お話しいただいた〇〇事業について、今後の展望や課題について、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」
- キャリアや成長に関する質問「貴社で活躍されている若手社員の方に共通する特徴や、仕事への姿勢があれば教えてください」
- 面接官個人に関する質問「差し支えなければ、〇〇様がこの会社で働き続けている一番の魅力や、やりがいを感じる瞬間について教えていただけますか?」
一方で、調べればすぐに分かること(福利厚生など)や、給与や待遇に関する質問(特に一次面接など初期段階で)は避けましょう。また、「何か課題はありますか?」といったネガティブな聞き方ではなく、「より良くしていくために、どのような挑戦をされていますか?」のようにポジティブな言葉に変換する工夫も大切です。
表6:逆質問のGOOD/BAD比較
| 質問 | BADな例 | GOODな例 | なぜGOODなのか |
| 働き方について | 「残業はどれくらいありますか?」 | 「皆様は、業務の生産性を高めるために、 どのような工夫をされていますか?」 | 自分の権利主張ではなく、 貢献意欲と向上心を示せるから。 |
| 企業研究について | 「御社の主力事業は何ですか?」 | 「Webサイトで拝見した〇〇という新規事業について、 特に△△という点に興味を持ちました。 この事業の今後の展望についてお聞かせいただけますか?」 | 自分で調べてきた上で、 さらに深い情報を求めている姿勢が、高い意欲の表れとなるから。 |
| キャリアについて | 「昇進できますか?」 | 「将来的に〇〇の分野で専門性を高めたいと考えています。 貴社には、若手のうちから専門性を磨けるような研修制度や機会はありますか?」 | 長期的な視点でキャリアを考え、 会社で成長したいという意欲を伝えられるから。 |
面接後24時間フォロー:お礼メールと振り返りシート
面接は、部屋を出た(または通話を切った)瞬間に終わりではありません。面接後のフォローアップまで含めて「選考」と捉え、最後までプロフェッショナルな姿勢を貫きましょう。
まず、面接後24時間以内に「お礼メール・メッセージ」を送りましょう。必須ではありませんが、丁寧な印象と入社意欲を改めて伝える効果があります。この行動そのものが「コンピテンシー」でもあり、マイナスになることはありませんから、やっておきましょう。
メールは簡潔に、以下の構成で作成します。
- 件名: 「〇次面接のお礼【大学名・氏名】」のように、一目で内容が分かるようにします。
- 宛名: 会社名、部署名、面接官の氏名を正確に記載します。
- 本文: 面接の機会をいただいたことへの感謝を述べます。そして最も重要なのが、面接で印象に残った話を具体的に一文加えることです。「特に、〇〇様から伺った△△というお話から、貴社の社風を肌で感じることができ、入社意欲が一層高まりました」といった一文が、テンプレートではない、あなただけのメールにしてくれます。
- 結びと署名: 再度感謝を述べ、「ご多忙かと存じますので、ご返信には及びません」と一言添えると、相手への配慮が伝わります。最後に大学名、氏名、連絡先を記載します。
そして、もう一つ。あなた自身の成長のために「振り返りシート」を作成することをお勧めします。これは提出するものではなく、次の面接に活かすための個人的なメモです。面接で聞かれた質問、うまく答えられた点、うまく答えられなかった点、次回への改善点を書き出すことで、一回一回の面接が貴重な学習機会に変わります。この地道な振り返りが、あなたを内定へと導く確実な一歩となるでしょう。
就職活動ガイド:他の関連記事
MICE業界について知る