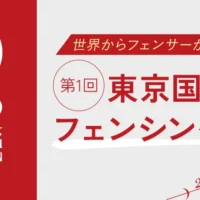【取材】南海電鉄が仕掛ける「インバウンド産業ツーリズム」ものづくりの街、泉佐野で地域資源を活かした集客のヒント:サステナブルなタオル生産
大阪から和歌山・高野山方面を結ぶ南海電気鉄道株式会社(以下、南海電鉄)。鉄道を走らせるだけでなく、沿線の価値を引き出す取り組みも行っています。難波から関西国際空港までの区間は、多くの人にとって“通過点”で、有名観光地が並ぶエリアではありません。そこで南海電鉄は、地元の工場や職人と手を組み、海外旅行者向けのツアーを企画しました。

「なぜ海外から人が来るのか?」「地域のコンテンツをどう活かせば、魅力的なツアーになるのか?」
そのヒントが、ここに詰まっています。今回は、ドイツからやってきた15名のグループがタオル工場を訪れる様子を取材しました。
こうした形態は“インダストリアルツーリズム”と呼ばれています。
工場や産業施設などの「産業」を観光資源として活用する観光形態のこと。

参加者はドイツからの企業経営者やマネージャークラスの団体
ドイツからの参加者は15名、主に企業経営者やマネージャークラスの方々が参加していました。所属する企業や業種はさまざまですが、共通して「新しい発見」や「将来のビジネスにつながる学び」を求めて来日。アジアの複数の国を巡る旅の中で、日本には3泊4日の日程で滞在し、そのうち1日を南海電鉄が企画する産業観光ツアーに充てていました。
スタートアップや環境にまつわる施設を1日で巡る
あらかじめ決まったルートはなく、南海沿線のネットワークを活かし、参加者の関心や目的に合わせて柔軟にプログラムを組み立てます。
当日のスケジュール
・大阪府内のスタートアップ施設を見学
・なんばパークスのパークスガーデンで生物多様性について学ぶ
・大学で最新の研究センターを見学
・泉州タオルを手がけるスマイリーアースの工場見学(★本取材の内容)

生命(いのち)を繋ぐタオルづくり
泉佐野市はタオルが生まれた地
大阪・泉佐野市は、国内におけるタオル発祥の地として知られる泉州地域に位置し、日本有数のタオル産地として発展してきました。南海本線で大阪・難波と関西国際空港の間にあり、大阪観光の拠点としても魅力的なエリアです。関西国際空港から大阪万博会場へのアクセスも良く、海外からの訪問にも適しています。
その泉佐野市の上之郷(かみのごう)にあるのが株式会社スマイリーアース。田んぼと山、そして民家に囲まれたのどかな場所で、タオルづくりの新たな挑戦を続けています。
「時間を惜しまなければ、環境に害のあるものは取り除けるんです」
そう語るのは代表の奥氏。

タオル業界では珍しい“一貫生産”を行います。もともとは分業体制の中でタオルを作っていたメーカーでしたが、タオル産業の衰退や、中国への生産拠点移転による価格競争で、最盛期のわずか1/10まで規模が縮小。関連会社が廃業したことで旧式の機械が手元に残り、それらを活用して環境負荷の少ないタオルづくりを、自社で一貫して行うようになりました。

時代と逆行?あえてアナログ製法を選ぶ理由
短時間で大量生産する時代の流れに逆らうように、あえて人の手間をかけたアナログ製法を選んだのは、品質への強いこだわりと、父の代から感じていた環境への課題意識があったからです。現在は奥さまを含む家族4人で製造を担い、サステナブルな取り組みを続けています。


その成果として、2015年には「循環型環境ストレスフリーを実現したタオル生産プロセス」を完成。2017年には「日本ストックホルム青少年水大賞」、2018年には「ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞」も受賞しました。
こんな工夫でツアーはもっと面白くなる
工夫点をお伝えする前に、まずはツアーの概要から。ツアーには通訳の方が1名同行します。家業の歴史から始まり、綿花や使用する素材、タオルの製造工程、そして排水の活用方法まで、ものづくりの背景を丁寧にたどっていきます。


所要時間はおよそ1時間ですが、参加者の興味や質問の内容によっては2〜3時間になることも。見学できる場所はオプションによって変わります。

では、ツアーの工夫点についてご紹介しますね。
1.心をつかむのはストーリー
汚染の歴史を知るために、スタート地点を変える
ツアーはいきなり工場には向かいません。バスで5分ほどの場所にある公園で集合です。

川沿いの道を走り、工場へ向かいます。そこで語られたのは、地元の2級河川「樫井川(かしいがわ)」が、かつて家業のタオル製造によって汚染されていたという歴史でした。

タオルづくりに使用する薬剤には発がん性物質が含まれ、農薬を使ったコットンの処理も当たり前だった時代がありました。上之郷には下水道がないため、排水は直接川へ流れ込みました。化学用品をつかう経済の中に身を投じると、薬剤からの呪縛から抜け出せなかったのです。
1998年には全国河川水質調査で「日本で最も汚い川」に選ばれました。今では澄んだ川になっていますが、その変化の裏には、環境負荷と向き合い続けた歴史があります。当時、小学5年生だった奥氏は環境調査をきっかけに、家業への罪悪感を抱きます。

一度は家業を離れたものの、「コットンを守るためにはどうすればいいのか」と葛藤する父の姿に背中を押され、再びタオルづくりの道へ。父と共に技術を磨き、命を守るものづくりへと舵を切りました。

ほら、こうして背景を知ると、川の見え方が変わってきませんか?
工場を止めて伝えたい、自分たちの「ものづくり」の存在意義
工場見学と聞くと、多くの人は機械が音を立てて動き、製品が次々と作られていく様子を思い浮かべるかもしれません。でも、このツアーではあえてそうはしません。
タオルを織る瞬間を見せることよりも、「どんなビジョンを持っているのか」「1枚のタオルができるまでにどんな背景があるのか」「何のために、どんな思いで作っているのか」という“本質”を伝えることを大事にしているからです。
伝えたいことを一つひとつ整理し、「本当に伝えるべきことは何か」を見極めたうえで話す…。そこにあるのは、製造工程の紹介ではなく、ものづくりに宿る価値を伝えたいという思いです。職人の信念や想いを、真っすぐに届けようとする強い意志が感じられました。

2.技術でなく“思想”を持ち帰る
ツアーで持ち帰れるのは、製造方法や技術はもちろんですが、その根っこにある”思想”です。テーマはサステナブル、ものづくり、経営、そして0から1を生み出す発想。製造業でなくても、自分の事業に置き換えて学べるヒントがあります。

奥氏に「参加者は何に興味をもたれますか?」と尋ねると、「従来のタオル製造から新しい製造方法へ移行したことや、ものづくりのイノベーションを生む環境ですね。愛知県のトヨタ博物館から来られる方もいて、歴史や背景への興味も大きいようです」と答えてくれました。

地域に土着できるものづくり、Nature Towel Factory(自然と共生するタオル工場)
製造工程に独自の工夫があります。従来のタオルづくりに必要だった大量の化学薬剤は技術開発でほぼゼロに。

奥氏が保有する山林で間伐した間伐材を燃料にすることで、化石燃料依存からの脱却を実現しています。

さらに、排水を貯水するプールでは、メダカやアマエビが繁殖できる水質に。


工場横の温室ハウスでは、工場排水を使ってバナナが育てられています。自然とものづくりが共生し、循環する「エコシステム」が息づいていました。
購入できるのはここだけ、触って確かめられる
見学の最後には、工場併設ショップでタオルの手触りを確かめられる時間があります。


ファクトリーブランド「真面綿(まじめん)」の商品は、工場併設のショップとオンラインのみの限定販売。
バスタオルは9,900円、ブランケットは20,000円。決して安くはありませんが、ここに来た人たちはその製品が持つ価値を納得して購入してくれています。

3.南海電鉄と事業者の二人三脚
南海電鉄とスマイリーアースさんとは密なコミュニケーションを取られている印象を受けました。受け入れ側だけでも、企画側だけでもなく、互いに力を出し合う姿勢が参加者の満足度を高めているのだと思いました。

新たな客層が見られた
スマイリーアースが工場見学を始めたのは2018年。南海電鉄との連携は今回が2回目で、来訪者の多くは海外から、日本の新しい取り組みを学ぶ研修として訪れます。ファミリー層よりもグループ旅行やインセンティブツアーが中心です。国内では修学旅行の受け入れもあります。今回のドイツからの来訪は、南海電鉄との企画だからこそ実現した、新たな客層だったといいます。
南海電鉄「新しい切り口でアピールし、工場側にもメリットを」
どのように地域の企業と連携をしたのかと南海電鉄に尋ねると、大阪府内のオープンファクトリーの定例会などに参加し、海外向けに取り組みたい企業を募ったそうです。こうしてインダストリアルツーリズムへとつながっていきました。
「”産業”という切り口で魅力をアピールし、沿線を応援したいですね。これまで国内向けだった取り組みを海外向けにも広げることで、工場側には新たな収益や企業活性化の機会が生まれます。訪れた海外の方には、ぜひ体験を母国で広めてほしいです」
双方に利益がある形をつくることで、継続しやすくなりますね。

さらに得られる効果
海外から人を呼び込むことは地域経済を動かす原動力となります。奥氏は「地元の人ほど自分たちの住む場所の価値に気付きづらい。海外の方が訪れて、『Exciting! 』と驚くことで、忘れかけていたふるさとの価値に気づける。だから、あえてここに来ていただくのです」と話します。
双方の理解があり、受け入れる姿勢があるからこそ、成り立ちます。結果的に地域経済やモチベーションを押し上げる効果があります。
海外参加者が求めるのはイノベーションのヒント
見学中、参加者たちは時折カメラを構えたり、熱心に質問を投げかけたりしながら、最後まで真剣な表情で耳を傾けていました。

ツアーの最後には、感謝の気持ちを込めてドイツ製のミッキーマウス人形を手渡す場面もあり、参加者は満足そうにタオルを購入。奥氏と握手を交わし、笑顔で別れの挨拶をしていました。

参加者の声「ここでの学びは将来のイノベーションにつながるはず」
ドイツの旅行会社に勤めるファービアンさんは、将来の観光やビジネスのトレンドを探るために参加。これまでにサンフランシスコやシリコンバレー、シンガポールなど世界各地を巡ってきました。工場見学を知ったきっかけは、インターネットでのリサーチでした。
「他国の将来の問題や、イノベーションに興味がある企業が参加していると思います。ここでの学びは、きっと将来のイノベーションにつながるはずです」と話してくれました。

Editor’s note:観光地がなくてもできる、地域に人を呼び込むヒント
今回のツアーが示したのは、観光資源の少ない地域でも、ストーリーと連携体制で人を集められることを示してくれています。
ツアーには「入口」「核となる部分」「出口」が用意されていました。見て・触れて・体験する導線が、見学以上の価値を生みます。本ツアーでは周辺の川から始めることで、ストーリーを伝えていました。次は、核となる部分、すなわち情報の選択と編集です。工程をただ見せるのではなく、何を持ち帰ってほしいかを軸に据えます。出口には“触れて買える”体験が用意されていました。
まずは一日で回せる短いコースを試し、反応に合わせて磨いていく…。自分たちの地域でも、入口・伝える核・出口、この三つをそろえることから始めてみませんか。

ツアー概要はこちら
沿線企業との共創で地域の魅力を伝える。オープンファクトリー
https://www.nankai.co.jp/contents/action/community_list/open_factory.html大阪の産業観光で、ものづくりの魅力を体感しませんか?
https://matcha-jp.com/jp/23218
株式会社スマイリーアース
https://smileyearth.co.jp
SDGs・ウェルビーイングに関する記事はこちら
ものづくり・オープンファクトリーに関する記事はこちら